あなたのバンドが伸び悩んでいるときに試したい4つのポイント
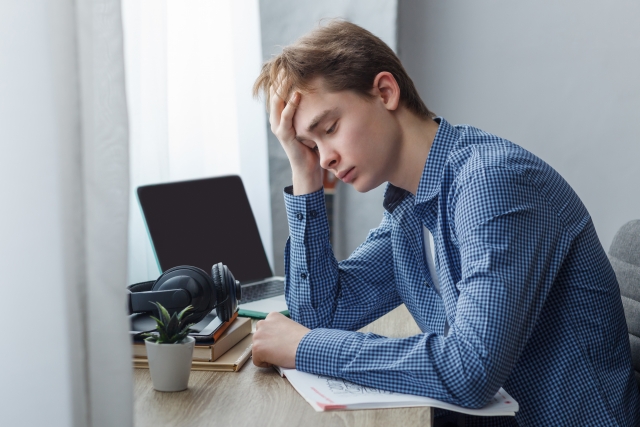
バンドの練習(リハーサル)でなんとなく演奏していませんか?
「間違わずに演奏できた!」そんな悩みは解消したけれど「ここからどうして良いかわからない」という声もよく聞かれます。
あなたもバンドの練習でそんな風に感じたことがあるでしょう。
そこで演奏をステップアップするための簡単な「秘策」をお伝えしましょう。
いや「秘策」でもなんでもありません。
誰もが知ってることを実際にやってみるだけです。
Contents
リズムをあわせる
よく聞く「リズム」という言葉の正体はなんでしょう?
リズムの正体を知る
ここでは、ある規則性(フレーズ)をもってビートの中に現れる音を「リズム」と呼ぶことにします。
リズムはいくつかの音符を組み合わせてできています。
1個や3個の場合もあれば、休符を組み合わせて使うこともあります。
これらの組み合わせを自由に使いこなせることがバンド演奏ではとても重要なのです。
リズムをみがくことは素晴らしい演奏への近道と言っても過言ではありません。
リズムの型を知る
リズムの組み合わせは多くありません。
16分音符の符割であれば16種類しかありません(便宜上3連系を除きますが、考え方は同じです)
この16種類を制覇すれば、あなたもリズムマスター間違いなし!
カギカッコで挟まれた「〜」が1拍と考えてください。
「○」は音符を、「・」は休符を演奏するところ。
そう考えると4拍子の1拍は以下の16種類で表されます。
(ここでは音符の長さは16分音符)
「○・・・」「・○・・」「・・○・」「・・・○」
「○○・・」「・○○・」「・・○○」「○・・○」
「○・○・」「・○・○」
「○○○・」「・○○○」「○・○○」「○○・○」
「○○○○」「・・・・」
これらを無機質に演奏できるようになることがポイントです。
無機質というのは「気持ちが込められていない」という意味ではありません。
アクセントや音色の変化がなく、的確にそのポイントで音を出せることを言います
流暢に演奏できるだけでなく、すべての音が「音量」「音色」ともに同じであることが重要なのです。
リズムの型を応用してみる
同じリズムでも音程が変わったり、違う楽器で音を出すとリズムの崩れてしまうことがよくあります。
前出である以下のリズムを例に説明しましょう。
「○○○・」「・○○○」「○・○○」「○○・○」
ドラムセットを例に「K(キック/バスドラ)L(左手)R(右手)」として考えると、このように表記できます。
「RLK・」「・RLK」「R・LK」「RL・K」
これらを組み合わせて練習することで「曲の中で突っかかる」「急に力が入る」ことが少なくなり、自然な演奏を実現することができるようになります。
音程楽器の場合は「ドレミ」を当てはめることで実現できます。
「ドレミ・」「・ドレミ」「ド・レミ」「ドレ・ミ」
この練習方法は個人練習向けですが、驚くほど効果があります。
もちろんバンド練習でも効果絶大です。
少ない時間でもかまわないので、ぜひ継続的に続けてください。
ドラム以外のパートにもリズムは重要です。
有名な曲として、Deep Pupleの「Smoke On the Water」を例にあげてみましょう。
口で歌うと「ジャッジャッジャーン、ジャッジャッジャジャーン、ジャッジャッジャーン、ジャーンジャーン」です。
楽譜にするとこんな感じです。
「♪r♪r♪rr♪|r♪r♪♪−−」「♪r♪r♪rr♪|r♪−−−」
この譜面をさきほどの16種類のリズムで置き換えてみるとこうなります。
「○・・・」「○・・・」「○・・・」「・・○・」「・・○・」「・・○・」「○・・・」「・・・・」
「○・・・」「○・・・」「○・・・」「・・○・」「・・○・」「・・・・」「・・・・」「・・・・」
驚くほど簡単に感じませんか?
そしてこのリズムを意識するだけであなたの演奏は驚くほど素晴らしく進化します。
ぜひ、個人練習やバンドで試してみてください。きっとあなたにも実感できるはずです。
全員でメトロノームに合わせてみよう
よく「ドラムに合わせよう」という表現があります。
もちろん間違いではありません。
しかし、全員が同じテンポとリズムで演奏するならば、全員がメトロノームに合わせて練習するのが一番です。
これはドラマーのテンポキープ力を批判しているのではありません。
Aメロはギターが急いでる、サビはドラムが音を引っ張り過ぎてる。そういうことが明確に分かるようになるのです。
「このセクション、自分では早く感じていたけれど意外とゆったりなんだな」
そういう気づきがあるのもメトロノームならでは。
バンドのノリが悪いときに「自分のリズムが悪いからだ」と悩むドラマーさんが多すぎ。
もちろんリズムやテンポをキープする役割はドラマーさんが重要なポジションです。
そして多くの場合で他のパートの人もドラムが原因だと考えていたりします。
しかし、バンドはひとりで演奏するのではなく、バンド全員で演奏するもの。
特定の誰かが悪いのではなく、メンバー全員のリズムを矯正する必要があると考えてみてはどうでしょうか。
ぜひ個人練習だけでなく、バンドの練習でもリズム練習を活用しましょう。
もしバンド全員がメトロノームに合わせて演奏できるなら、そのバンドは素晴らしいリズム感を持っていると断言できます。
音の長さをそろえる
音を出す瞬間の話はわりとよく聞きますが「いつまで音を出すか」という「音の長さ」についてこだわっている人は意外と少ないもの。
音の長さをコントロールする
ダンス音楽におけるベースでは特に重要なのが「音の長さ」。
そのビートがやってくると同時に音を出し、次のビートがやってくると同時に音を消します。
音を切る瞬間が「休符」を演奏するタイミングなのです。
「音の長さ」を意識する・しないではバンド全体で演奏したとき、大きな違いがあります。
ぜひ意図的に音の長さをコントロールしてみてください。
またフレーズを優先するあまり「フレーズ映え」にこだわることでリズムが軽くなることがあります。
また、ルート音で8分音符を弾き続けるようなフレーズでも「音の長さ」が一定しない演奏だと心地よく聴けないもの。
「4分音符」は「4分音符」に、「8分音符」は「8分音符」として聴こえるように演奏する。
そのようにリズムと同時に「音の長さ」も意識して演奏しましょう。
もちろんギタリストとベーシストなどで「フレーズの音の長さ」について話し合っておくことはとても重要です。
音程を明確に
楽器を演奏していると、自分の担当楽器の「音色」「特徴」を出すことに集中してしまいます。
しかし多くのお客様は歌(メロディ)を聴いています。
歌(メロディ)を伴奏する意識も忘れることなく楽器を演奏しましょう。
音の立ち上がりからその音程を出す
「歌」「メロディ楽器」は音の出だしからその音程を発音できるようになりましょう。
もちろんズレたりすることなく。
音が立ち上がる瞬間から音が変わる瞬間までその音程をずっとキープするのです。
立ち上がりに不安があると「音を探る」クセが付いてしまいます。
これはなかなか自分では気づかないので、誰かにチェックしてもらいましょう。
もしくは、自分の歌や演奏が「探った演奏」になっていないか録音した音源を繰り返し聴きなおし、自分の演奏をチェックする癖をつけましょう。
音程差を意識する
吹奏楽の経験者ならご存知と思う練習方法「ドミレファミソファラソシラドシレド~」
音程差を維持しながら音域を変化させていく練習方法です。
楽器は歌よりも音程差をとりやすい傾向があります。
しかし絶対ではありません。
ギターやベースではポジションや奏法によってわずかに音程をベンドさせてしまうことがあり、私もプロのベーシストから指摘されたことがあります。
歌でも音程差を維持しづらい音域があると思います。
そういうときは鍵盤楽器を使ってフレーズの音を確かめてみましょう。
歌い始めは良くても、歌い終わりの音程がズレていることはよくあります。
あなたが特別なのではありません。
みんなズレに気付かないのです。
意識して練習することで一気に解消することができます。
レッツトライ!
フォームを見直す
お客様からの見栄えをよくするためにも大事ですが、魅力ある音を演奏するためにもフォームは大切です。
前を向こう
演奏をする上で最も大切なことのひとつに「お客様の方を向く」が挙げられます。
お客様は「ミュージックチャージ/入場料」などの「お金」だけでなく、誰もが大切にしている「時間」を割いてあなたの演奏を観に来てくれています。
さらに、最も敬意を表してほしいポイントはあなたの演奏を観にいこう、そう決めてくれた「気持ち」です。
演奏に精一杯なのも最初は仕方ないことでしょう。
しかし気持ちの上でお客様の方を向くことはとても大切です。
誰かに向けられた演奏はとても素晴らしい「パワー」を持っています。
その場に来てくれた「誰か」のためにあなたの演奏を届けましょう。
立ち姿勢と座り姿勢
ドラムやキーボードは座って演奏するかもしれませんが、その他のパートは立って演奏することが多いでしょう。
この「姿勢」も重要な音楽的要素です。
学生時代、バンドコンテストに出たことがあります。
コンテスト後に審査員の方と話す機会があり、どういう観点で審査されているか聞いてみました。
そのとき真っ先に出てきたポイントは「フォーム」でした。
「正しいフォームでなくても音は出るけれど、正しいフォームで演奏された音はシンプルで美しい」
その言葉は今も大切にしています。
多くのスポーツでそのフォームをチェックし修正します。
野球やテニスでもフォームを安定させるために素振りをしますね。
楽器演奏でも同じです。
正しい「姿勢」から身体に無理のないフォームで音を鳴らしましょう。
無駄のないフォームから奏でられる演奏ではその音色も魅力的。
また誰もが憧れる速い演奏にも対応できるようになります。
実際に、スポーツをされている方の演奏フォームは美しい場合が多いです。
フォームの大切さを知っているからこそ演奏方法にも出てくるのでしょう。
あなたの好きなアーティストがカッコいい理由にフォームが関係しているかもしれませんね。
演奏に使う筋肉と関節の確認
姿勢が意識できたら、次はストロークを見直してみましょう。
ギターやベースではストロークという言葉は分かりやすいかもしれません。
音を出すための腕の振りなどをストロークと呼びます。
人間には関節があります。
この関節を動かしているのが筋肉です。
筋肉のどの部分を「緩める」「緊張させる」という意識が演奏を際立たせます。
よく「力を抜いて」と言われませんか?
しかし抜きっぱなしでは音楽になりません。
適度な「入れ方」「抜き方」があるのです。
自然に体得してしまう天才肌の人もいます。
フォームだけでなくストロークも意識して力の「入れ方」「抜き方」を手に入れましょう。
今日のおさらい
- リズムはドラマーだけでなくバンド全員の問題
- 音の高さだけでなく「長さ」にも注意してみよう
- 音程を正しく
- 美しい演奏は美しいフォームから生まれる
どうでしょうか。意識するだけでできることが多くありませんか?
以前クリスコールマンも言っていました。
「簡単なことだけど、続ける人は少ないんだ」
世間でいう天才とは小さな努力を継続して続けている人のことかもしれません。
